フランスで流行の伝統菓子 「フラン」
[前編]フランの歴史
近年、フランスで伝統菓子「Flan(フラン)」が流行しているという話をよく聞く。
現地の新聞や雑誌ではしばしば「パリのベストフラン(Meilleurs Flan à Paris)」のような記事が組まれるほど、メジャーな菓子だ。
日本のパティスリーではあまり目にすることがないこのフランについて、これから3回にわたり様々な視点から紹介していこうと思う。
最初の[前編]ではまず、フランのルーツや背景について触れていきたい。

そもそも日本でフランというと、フレンチレストランで出て来る前菜「カニのフラン」のようなものを思い浮かべる方も多いのではないだろうか。ブイヨンに卵とその他の具材を入れてココットで蒸し焼きにした、まるで日本の茶わん蒸しみたいな料理である。一方でスペイン語圏の人々は、フランと聞くと日本のカスタードプリンのようなデザートを思い浮かべることが多い。
地域によって実にさまざまな形で存在しているフランだが、全体像を掴むため、まずはフランの起源から見てみることにする。
ローマ時代まで遡る、フランの歴史
2019年に出版されたステファン・グラシエシェフ(MOF)による著書「Flan Gourmands(フラン・グルマン)」にはシンプルなヴァニラからフルーツを加えたもの、卵不使用やグルテンフリーなどまで、実に20種類以上のフランのレシピが紹介されている。
基本的には家庭向けのレシピだが、フィユタージュなどはすべてスクラッチで紹介されていて、プロのパティシエが読んでも十分得るものがある良書だ。そのレシピ集の中に、フランの歴史が2ページにわたって詳しく書かれている。
同書によると、ローマ時代の料理書「Apicius(アピシウス)」には「TIROPTINAM(ティロパティナム)」という名で、すでにフランに近いレシピが紹介されていたという。
「牛乳に卵とハチミツを加え、混ぜながら加熱し、炊き上がったら胡椒をふって仕上げる。」
現代人からするとちょっとイメージがわきにくいかも知れないが、卵・ハチミツ・胡椒はすべて当時の高級食材なので、きっと庶民には手の届かないデザートだったのだろう。

中世以降の発展
中世には「Flado(フラド)」という名のケーキがヨーロッパ中に広まり、14世紀のフランスではすでに現在のフラン(パート(生地)の中にアパレイユが詰まっているタイプ)と同じものが見られたという。
このころのスペインでは同じ名前を持ちながらも、生地は使わないタイプのフランが出現している。
フランス国内でもブルターニュ地方の「ファーブルトン(Far Breton)」やリムーザン地方の「フロニャルド(Flognarde)」など、フランから派生した地方菓子や料理がいくつも存在しているが、それらにも生地は使われていない。世界的に見ると、ひょっとしたら生地を使わないフランの方が多いのかもしれない。
手元にある1950年出版の「Traité de Pâtisserie Moderne(現代フランス菓子概論)」には9種類のフランが掲載されているが、現代のフランス人が思い浮かべる一般的なフランは「Flan Parisien(パリ風のフラン)」として紹介されている。その他のレシピは「ポーランド風」「ブルターニュ風(ファーブルトン)」などと呼ばれている点から考えると、フランのバリエーションは20世紀になってもまだ増え続けており、一方でシンプルな「パリ風のフラン」もさらなる進化を遂げていたことが想像できる。
このプロセスは、同じ伝統菓子の代表格「マカロン」にも当てはまるだろう。
フランス国内にはあらゆる地方の名を冠した独自のマカロンが存在しており、日本で定着しているマカロンも正式には「マカロン・パリジャン」と呼ばれる、パリで洗練されたタイプのものだ。(フランスの各地方に残る本来のマカロンは、もっと素朴な菓子である )
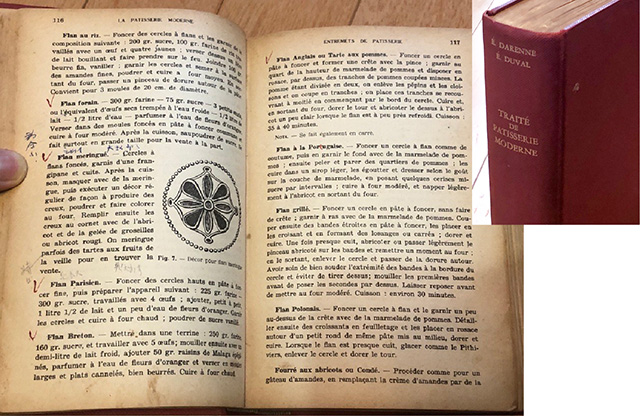
参考までに「Traité de Pâtisserie Moderne(現代フランス菓子概論)」掲載の「Flan Parisien(パリ風のフラン)」のレシピを和訳しておく。
背の高いセルクルに薄くのばしたパータフォンセ(※パートブリゼ/練りパイのこと)を敷きこむ。
全卵4個(※約200g)に小麦粉225g、グラニュー糖300gを混ぜる。
1.5ℓの牛乳を少しずつ注ぎながら混ぜ、最後に少量のオレンジフラワーウォーターを加える。
高温のオーブン(※200℃前後)で焼成する。
仕上げにヴァニラシュガーを振りかける。
古い本のために作り方も今ほど詳しくなく、仕上がりをはっきりと想像するのは難しい。しかし卵が少ない上にアパレイユに粉が多いことなどから考えると、現在のような濃厚で滑らかな舌触りではなく、少しもたっとした食感になるのではないかと思う。
まとめ
古代にはすでにその原型が登場し、各地でガラパゴス化しながら広がって行ったフラン。時代の流れや文化の壁も「独自進化」という強みで踏み越えて脈々と生き続ける─そんなシンプルな伝統菓子こそが持ちえる力を感じていただけただければ幸いである。
次回[中編]では本場パリにおける「フランの今」をお届けする予定なので、ぜひお楽しみに!







